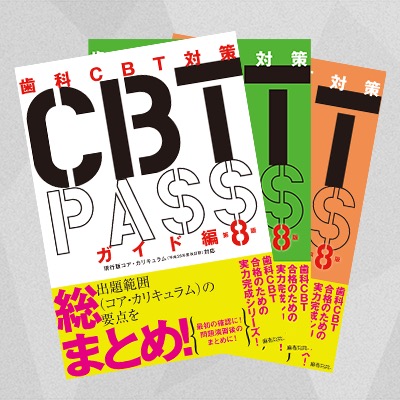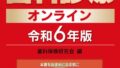こんにちは!今日からは、とある人からの助言により、敬語で文章を書いていきたいと思います。そっちの方が何かいい感じがするそうです(笑)
早速本題です。本日、上に示している本は、歯学部生3,4,5年生あたりが購入して使用する可能性が高いCBTのテキストのガイド編です。(参考文献:https://www.azabu-dental.co.jp/category/CBTPASS/BOOK_CB_S0_2025.html)
歯学部のCBTは、他の試験と比べても、留年になってしまう可能性が高い試験であり、間違った取り組み方や不十分な勉強量では、落ちてしまう可能性が高いです。基本的には、4年生か5年生で実施されることが多く、本試験に落ちてしまった場合は再試験を受けることができます。(しかし、そろそろ再試験が取りやめになるらしいです。)この試験は、国が管轄で作っている試験であり、この試験とOSCE(オスキー)と言った臨床実技の力を測る試験の二つに合格することで、附属病院等における臨床実習が許可されると言った感じのイメージです。
この試験のポイントは大きく4つあります。
①多くの問題がプールされており、その中からランダムに問題が出題される
CBTの試験範囲は国家試験と類似しており、その範囲の中から2000問とか3000問とかの単位で問題が作られており、その中からランダムに数百問選ばれて出題されると言った感じです。これだけ聞くと不公平な感じが若干しますが、問題ごとに全体の正解率等を分析し、1問1点ではなく、それぞれの問題で正解時・不正解時のポイントの差を上手く付けているから、そこまで不平等にはならないのです。
②問題の選択肢は5つで択一式である
歯科医師国家試験は、1つ選べ・2つ選べ等からすべて選べまで、選択肢を何個選ぶかは問題によります。CBTは問題の難易度も国家試験よりもかなり低くなっており、それも択一式であるので、当然歯科医師国家試験よりも難易度はかなり下がります。
③CBT PASSの3冊で十分である
歯科医師国家試験と違い、参考にする教材は必ず医歯薬出版の教科書ではなくてもよく、今回上の画像でも載せたCBTガイド等の麻布デンタルアカデミーから出版されている教材でも十分であるということです。実際、私がCBTを勉強するときは、CBTガイドの内容をできるだけ隅々まで読み込みつつ覚えながら、少しだけ医歯薬出版の教科書を見て、付随している問題集の問題を解いただけで全体の正解率は95%くらいでした。サンプル数が私1人だけでは十分ではありませんが、基本的には全国の受験生は、麻布デンタルアカデミーから出ているCBTの教材くらいしか使ってませんし、CBTの出題範囲をできるだけ網羅できるように作られている教材なので、これを十分に勉強すれば問題ないのです。
④CBTの合格基準は大学毎の基準による絶対評価である
CBTの試験は絶対評価であり、相対評価ではないということです。CBTの合格基準は大学ごとに何%と決められており、他の人が何点であっても自分の点数が合格基準を超えていれば合格なのです。ですから、歯科医師国家試験に比べて、周りの受験生は敵ではなく、仲間感が強いかもしれませんね(笑)
本日は、歯学部の学生が越えなければならないCBTについて書きました。この試験は、その時までにあった定期試験よりもボリューミーで、尚且つ留年生も出がちな試験ですので、歯学部生はしっかりと『正しい』準備をして挑みましょう。
本日のブログは以上です。ありがとうございました!