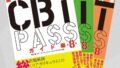臨床研修が始まり、指導医の先生がやる治療を見学することが中心でしたが、たまに治療の機会を与えてもらい、治療することも増えてきました。実際の手技については、大学での各授業での実習や附属病院での研修で少し練習したくらいですので、ほとんど手は動かず、毎日四苦八苦です。
しかし、日々臨床を学んでいく中で、教科書や大学の授業で学んだことと臨床のギャップを感じ始めています。具体的な例をいくつか挙げながら書いていきます。
1つ目は、根管治療についてです。Per(歯の根に病気がある状態)があるときには、まず根幹の中の病的な象牙質等を取り除き、洗浄液で洗い流すという治療を何度か来院してもらい繰り返した後に、根管充填といって詰め物を歯の根っこに詰める治療をします。教科書的には根の先端部の病巣がなくなるまで根っこの掃除を行って、病巣がなくなってから詰め物をする、ということで学びました。しかし、臨床的には症状が無くなり、改善傾向になれば、病巣が少し残っていてももう詰め物をするという流れのようです。確かに、患者さんの来院回数やチェアタイム(患者さんが治療代に座っている時間)を考えるとそうするしかないのが現実ですが、できる限りエビデンスにできるだけ基づく治療をどうにか考えていきたいです。
2つ目は、カリエス(虫歯)の治療です。虫歯がある患者さんが来た時、まずは目に見えて分かる虫歯の部分を取り除き、染め出し液を用いて、目に見えて分からない虫歯に色をつけて取り除きます。教科書的には、もちろん完全に取り切るように書かれていますが、臨床的には若干染め出されていても硬い部分は取り残したままにすることも多々あるようです。また、染め出されにくい慢性的なカリエスの部分もあるので、結論完全にカリエスを取り除くことは難しいのです。
3つ目は、ラバーダムの使用についてです。ラバーダムとは歯にかけるマスクのようなもので、口の中からの水蒸気や歯肉の溝あたりからの滲出液を防ぐことができ、防湿すること(水分を防ぐこと)ができる治療です。これをすることで、詰め物と歯の接着力を高めたり、治療で歯に使う薬剤が喉の方に流れるのを防いだりできます。学校では、これを使うことが治療の基本だと学んできましたが、臨床ではラバーダムはあまりしない、もしくは『自費』治療を選択してくれたらラバーダムを用いるといった形が多くとられています。これは、ラバーダムが保険算定上点数がなく(料金がかからない治療すなわちサービスであり)、ラバーダムの器具の準備にかかる経費を考えると、資金繰り上、歯科医院にはメリットが少ないからという理由が大きいです。もちろん、治療の精度、患者さんの予後を考えれば使用するべきなのですが、理想と現実のギャップは大きいです。
今回は、臨床と大学で学んだことのギャップをいくつかの具体例を挙げながら書かせてもらいました。歯科医師や歯科医院としてはあまり書かれたくない内容かもしれませんが、自分の今の思いや歯科医療業界の実態の一部を書き留めておけたらなと思い、書きました。まだまだ、臨床と教科書(エビデンスに基づいた治療)の乖離は存在しますので、また書かせてもらいたいと思います。
以上です。ありがとうございました!