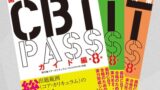はじめに
今回は、歯科医師国家試験における『食中毒』に関する問題の対策となる覚え方等について書いていきたいと思います。
①ウイルス性食中毒?細菌性食中毒?季節はいつに多い?
食中毒には、ウイルス性食中毒と細菌性食中毒があります。
ウイルス性食中毒は、ノロウイルス、ロタウイルス、A型肝炎ウイルス、E型肝炎ウイルス等が原因ウイルスとしてあります。
基本的には、ウイルス性食中毒は冬場に多いです。冬場は牡蠣小屋で牡蠣を食べることが多いですよね。そこから、食あたりになるとノロウイルスになるなあ、と考えると、冬場にウイルス性の食中毒が多いのも理解できると思います。
細菌性食中毒は、黄色ブドウ球菌、ボツリヌス菌、セレウス菌(嘔吐型)、サルモネラ属菌、カンピロバクター、セレウス菌(下痢型)、腸炎ビブリオ、腸管出血性大腸菌(O157)、病原性大腸菌、ウェルシュ菌等が原因菌としてあります。
基本的には、細菌性食中毒は夏場に多いです。おにぎりを汚い手で握って、そのおにぎりを後で食べて食あたりになるのは黄色ブドウ球菌が原因なことが多いです。夏場は、高温多湿であり、黄色ブドウ球菌がおにぎりの中で増殖しやすいことで発生します。だから、夏場は細菌性食中毒が多いのかと理解できます。イメージはなんでも良いですが、先ほどの冬場の牡蠣小屋しかり、このような感じで、どうにかして理解しておくと、暗記のハードルがかなり下がります。
②細菌性食中毒の毒素型?感染型?
細菌性食中毒の原因菌は、毒素型と感染型に分けることができます。
どの細菌が毒素型か感染型かの分類を頭に入れておかなければ解けない問題は、95回と99回の歯科医師国家試験での出題歴があります。古い出題歴であるため、出題要項的にももう入っていない可能性もありますが、どんな細菌が食中毒の原因となるかはまだまだ出題されかねない知識であると思われるため、毒素型・感染型の分類はついでで覚えるつもりで、食中毒の原因細菌を下記のゴロ合わせで覚えておきましょう。
・毒素型
毒吐くセレブなボー
毒→毒素型、吐くセレ→セレウス菌(嘔吐型)、ブ→(黄色)ブドウ球菌、ボ→ボツリヌス菌
・感染型
かーんサルのかんちょうセレコウェルカム
かーん→感染型、サル→サルモネラ菌、カン→カンピロバクター、ちょう→腸の字が付く細菌、セレウス菌(下痢型)、コ→コレラ菌、ウェルカム→ウェルシュ菌
③食中毒についての法律の規定
食中毒発生の防止についての規定や食中毒患者発生時の保健所への届出の規定は、食品衛生法で行われています。保健所の設置については健康増進法で定められているため、食中毒患者発生時の保健所への届出も健康増進法で定められていると間違われることがありますので、注意しておきましょう!
食中毒発生の防止についての規定や食中毒患者発生時の保健所への届出の規定
⭕️ 食品衛生法
❌ 健康増進法
おわりに
今回は、歯科医師国家試験の『食中毒』についての肝心な部分だけをピックアップして書きました。もちろん、今回挙げた細菌やウイルスの詳細は、歯科医師国家試験の『感染・免疫』の分野で非常に問われやすい部分ですので、CBTガイド(下記URL参照)に書いてあることくらいまでは、『暗記』のレベルまで知識を整理しておきましょう!それでは、今回もありがとうございました!